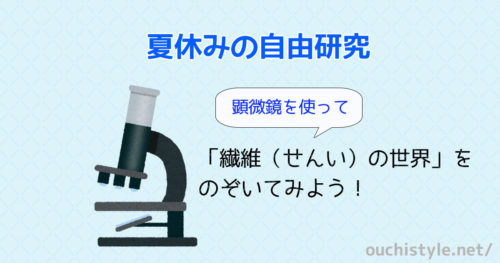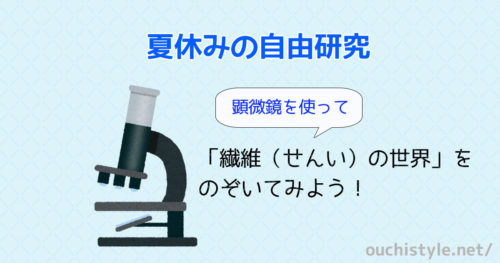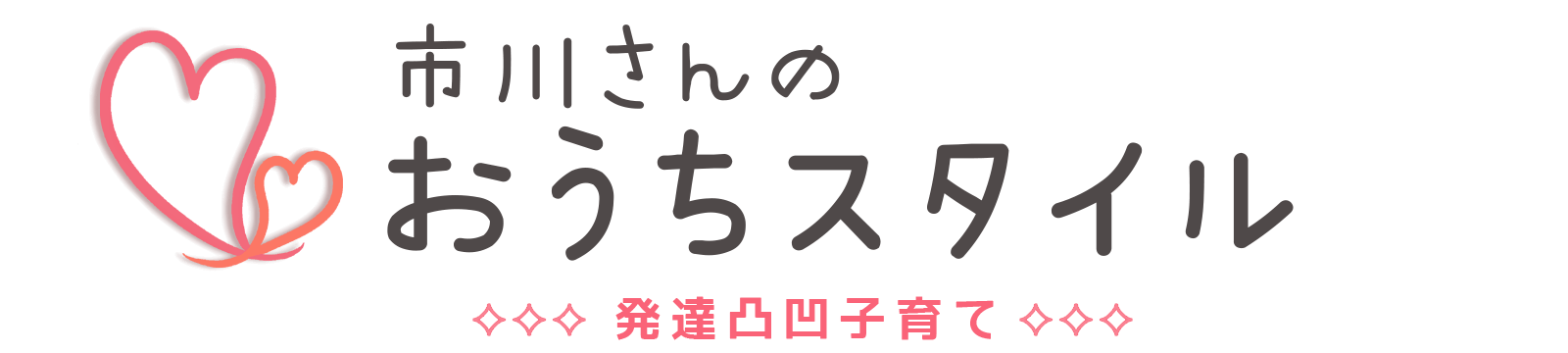春になると、潮干狩りのシーズン到来ですね!
子供も大人も夢中になる潮干狩りですが、楽しいだけで終わらせず、ついでに自然学習もしちゃいましょう。
こんな日常のことでも、よくよく観察したり考えてみると、大事なポイントがいくつも発見!自由研究にもなりますよ♪
潮干狩り・アサリの問題が中学入試に
潮干狩り
潮干狩りで一生懸命に採ったアサリをお持ち帰りし、さぁ、お味噌汁に!と、すぐには食べられません。
砂抜きをしないと、ジャリジャリしたアサリを食べることになってしまいます。
大人からすると、今まで経験してきた感覚で、「そんなこと知ってるよ~」と思うかもしれませんが、そこまで知らないのが小学生。
しかも、入試問題で実際に出題されているんです。
慶應普通部2018年の理科
実際に、2018年入試問題・慶應普通部の理科でアサリに関する問題が出題されていました。
潮干狩りからアサリを持って帰ってきた時にはどんな状態か、どのように置いておくか、砂の中にいる時のアサリの絵を描くなど、「そういえば、どうなっていたっけ?」と、中途半端に覚えているだけではダメな問題ですね。
知っていればラッキー問題ですし、知らなければ何も手がでない・・・![]()
アサリの観察
活アサリを買おうと思った理由
娘が小学校2年生の時、日能研には通信教育なるものがあったんです。
(現在、日能研で通信教育「知の翼」は行っていません。)
娘は少しだけその通信教育をやっていた時に、おうちで実験してみようというのがありまして、「アサリの浄化作用」についてでした。
米のとぎ汁の中に、アサリを入れると水がきれいになる
という実験です。
アサリを見ると、潮干狩りへ行ったのはいつだったかな?娘はもうすっかり記憶にないだろうなと思い、再び実験してみることに。
潮干狩りに行く時間がないので、スーパーで販売されていたパックに入っている「活アサリ」を購入しました。
アサリの水質浄化実験
スーパーで買ってきたアサリが生きているのか確認するため、3%くらいの濃度の塩水につけて、アルミホイルをかぶせて、しばらく置きました。
すると、殻から元気に中身がでてきていました。
そこで、米のとぎ汁を少し入れて、水を濁らせ、アルミホイルをかぶせて暗くし、置いておきました。
 わたし
わたしとぎ汁を入れる量はどれくらいだろう???
塩水に色が付くくらいでよいと思います。最初、加減がわからなくて、濃いとぎ汁を入れてしまったところ、水の浄化に時間がかかってしまいました。


すると2時間後には・・・


そして、小さい沈殿物が底にいっぱいありましたが、米のとぎ汁でにごった塩水が透明になっていました![]()
![]()



水がきれいに透明になってる~!
この実験は結構有名なようで、たくさんの動画が投稿されています。
アサリの観察
アルミホイルをかぶせたまま、しばらくアサリを放置し、開けてみると、貝殻のすき間からデロデロと中身がでていました。


2本の管は口?と思われがちですが、入水管と出水管と呼ばれるもので、口ではありません。
海水と一緒にえさも取り込む入水管と、エラ通った水を排出する出水管が砂の中や水の中から伸びてきています。
しばらく見ていると、ピュー~ッと水が勢いよく吐き出されるので、砂抜きをする時やしばらく置いておく時はアルミホイルをかぶせないと、あちこちの方向に噴射されて水浸しになってしまいます。
この2本の管の反対側には、何やら平べったいものがデロ~ンと出ているのですが、これが足だそうです。
アサリの自由研究は幅が広い!
自由研究となると、観察だけで終わり・・・はボリュームが足りないですよね。
そこで、もうちょっと付け足しをするならば・・・
・ハマグリやシジミなど、スーパーでも入手できる二枚貝で貝殻の模様、大きさ、厚さ、中身の違いなどを比較する
・体のしくみを調べてイラストで説明する
・住みやすい環境を調べる
・アサリの天敵を調べる(固い殻があっても、天敵がいるんですよ~)
・二枚貝以外の貝についても調べる
・家庭科につなげて、調理してみる(ボンゴレ、味噌汁など)
・貝殻を使って、工作(貝殻に色を塗って、100均で購入した写真立てのフレームにボンドで飾り付け)



楽しそうなものばかり!
1日でできる自由研究なので、おすすめです。
他にも自由研究を紹介していますので、参考にしてください。